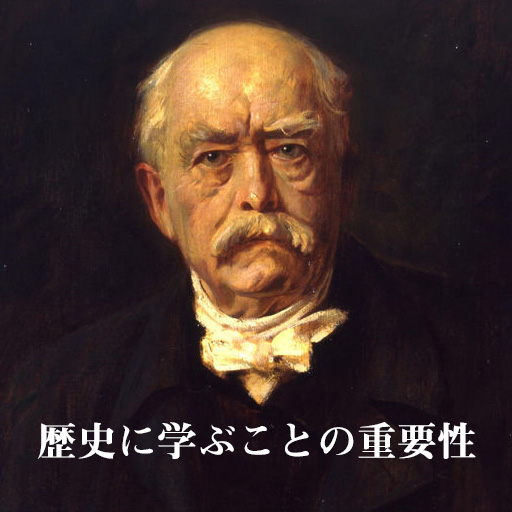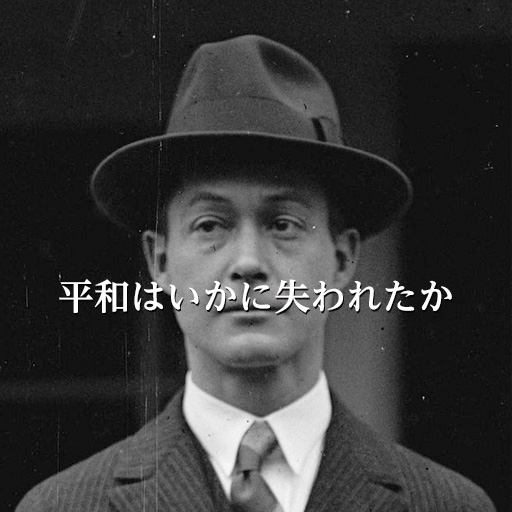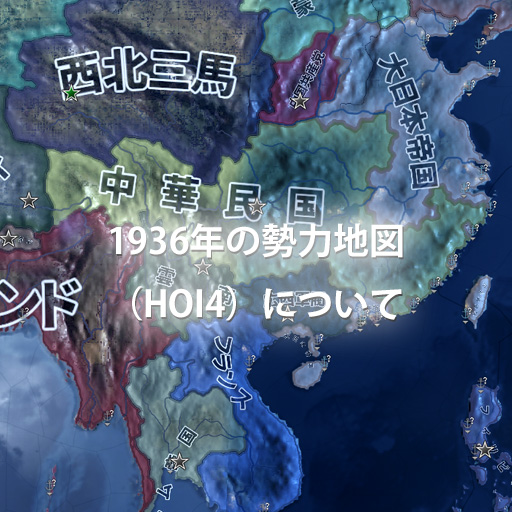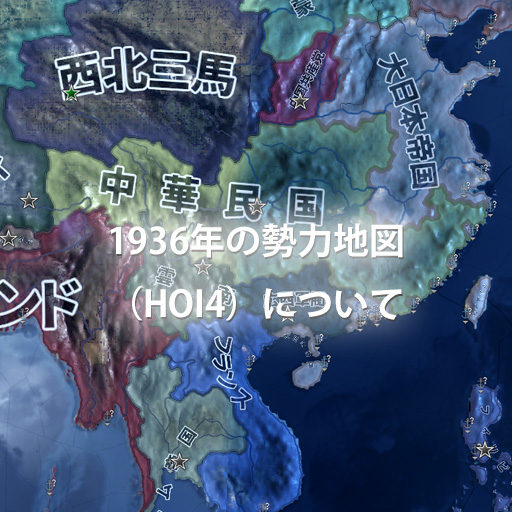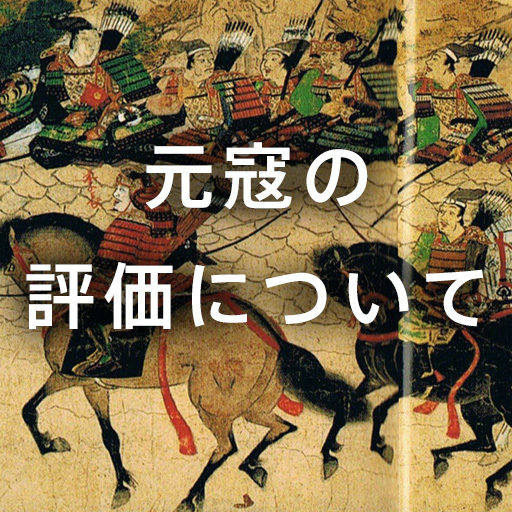中国共産党の歴史④

スポンサードサーチ
アジア共産化戦略推進組織設立
- 1949年4月「第1回平和擁護世界大会」ソ連主導
平和擁護というワードを隠れ蓑とした共産化活動(平和という名を使ったものは注意が必要) - 1950年9月 平和擁護日本委員会(日本共産党系)
- 1951年1月 全面講和愛国協議会
字面だけみると判りづらいですが、日本共産党、社会党左派、自治労、私鉄労連などが中心で全面講和と再軍備反対の署名運動開始。(当時まだサンフランシスコ条約<日本国との平和条約>が発行されていません)日本における工作のひとつ
「平和」という言葉を使っている組織、書籍、標語などの背景に共産党または共産党のフロントと化している社会党系、民主党系がいる場合が多いので、注意が必要です。
ヒロシマ、ナガサキ、アベ、フクシマなどといった「カタカナ」を利用した用語を使うのも共産党特有のアジテーション手法の一つです。
共産系の影響を受け、労働者の待遇改善より反米闘争を優先させる社会党
今は社会党から社会民主党に名前を変えましたが、やっていることは当時も今も変わりません。影響力は下がりましたが、分裂し名称を変えて今も同じ活動をしています。(民主党、国民民主党、立憲民主党など)
主張を見る限り共産党のフロントと言って差し支えない社会党は次のように主張を変遷させています。
- 1950年12月25日 社会党外交委員会「日本が国家として、その独立と領土とを守る自衛権は否定されるべきではない」※今と主張が正反対です。
- 「全面講和への要求をもっと明らかに」「再軍備に反対」 社会党左派
「基本は日本の独立であり、講和を優先すべき」 社会党右派 - 1951年の社会党大会にて、将来の再軍備を認める原案は否定され、「再軍備反対」「平和三原則(全面講和、中立堅持、外国軍事基地反対)」を決議
※共産党の日本国内の武力共産革命の障害となる3つの要素の反対
スポンサードサーチ
対日保守陣営工作の「日中貿易」
1952年4月28日にサンフランシスコ条約が発効され、日本の独立が回復されました。
翌月、帆足計元参議院議員訪中し、第一次民間貿易協定に調印しました。
1953年、超党派「日中貿易促進議員連盟」設立。事務局長松本健二の自伝に「革命民族戦線強化の立場からも保守党工作に全力を挙げた」と記載。
中国元女優が対日スパイとして活動し、日本の国会議員に接触し関係を持っていたというレポートが存在します。2002年5月2日産経新聞
1954年北京にて革命家養成学校が創設され、日本人の革命家を養成。3年間で約2500人育成。
細川内閣の官房長官である「武村正義」氏もその一人といわれる。(サンデー毎日 S36.3月特別号)
日本の敗戦後、満洲国の日本人指導者層や軍人を戦争犯罪者として抑留(1062名)
1017名が1956年に釈放され、帰国しました。(思想改造済み、共産党に協力する約束の上釈放)
日本に帰った「戦犯」とされた人々は中国帰還者連絡会を結成し「中日友好」に一役買いました。そのまま60年安保闘争にて活躍しました。
中国共産党の息がかかった工作員、帰国者は
- 日米安保体制の解体
- 日本の再軍備反対
- 日中国交正常化の推進
の3つを目指しました。
共産党の狡猾なところは、意のままに動く人間を用意し動かすだけではなく、反対する立場の陣営に工作員(意を受けた人材)を巧妙に侵入させることです。
これは当時に限った話ではなく、現在においても同じです。
保守系の団体・グループ・サークル、政治団体内にも巧妙に入り込んでいます。
真実に巧妙な嘘を混入させ嘘の普遍化を目指したり、意気をあげた主張で共産党に都合の悪い話を反らしたり、一見保守に見える主張を使っての思考誘導を行ったり、過激な論(ヘイトに近い論)を用いて味方の信頼度の低下を促したりといった活動を行います。
日本人は基本的に相手を信じますので工作を見抜くには、ブレない軸をもって味方と思われる人の主張も注意して確認する必要があります。
最近では、北方領土問題の解決を邪魔したというのが、判り易い事例です。
1957年、池田勇人氏が自民党「宏池会」を結成しました。
その「宏池会」というのは、現在の保守から悪評高い談話を出した河野洋平氏や宮沢喜一氏がいた所です。
この初代事務局長は田村敏雄氏なのですが、この方は「フジカケ」というコードネームを持つソ連のスパイです。(シベリア抑留で思想改造され、協力を約束した見返りに帰ってきた人)
「宏池会」という派閥はもともとそのような組織です。
池田勇人氏は田村氏がそういう系統だって分かっていました。が、あいつはそうじゃないと言って最後までかばっていたようです。
誤解のないように言及いたしますが、池田元首相自身はソ連のスパイでも何でもありません。
次回は中国の対アジア工作とアメリカの外交政策について言及します。
つづく
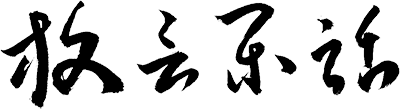
 記事が気に入ったら支持する!をお願いします。
記事が気に入ったら支持する!をお願いします。